
「優秀な人材が採用できない」
「せっかく採用しても早期離職してしまう」
「採用コストが年々増加している」
このような採用課題に頭を悩ませていませんか?
労働人口の減少により人材獲得競争が激化する中、場当たり的な採用活動では限界があります。
今こそ、経営戦略と連動した「採用戦略」を構築し、計画的に優秀な人材を獲得する仕組みづくりが大切です。
本記事では、採用戦略の基本概念から、実践的なステップの立て方、すぐに使えるフレームワークまで、採用戦略に関する内容を解説します。
国内最大規模の独立系RPOの
”レジェンダ・
コーポレーション”
創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上
ノウハウが詰まった
資料を大放出!
30秒で簡単入力、お気軽に
お問い合わせください!
採用ブランディング完全ガイド
全10ページの
実践ステップ搭載
無料ダウンロード
資料を受け取る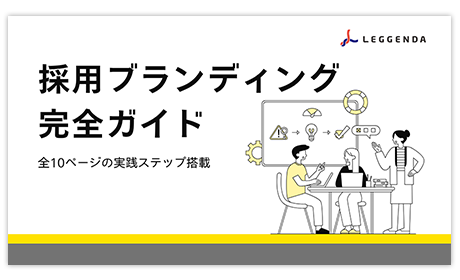 資料を受け取る
資料を受け取る
採用戦略とは、企業が経営目標を達成するために必要な人材を計画的に獲得するための方針と具体的な施策の総称です。
単なる人員補充ではなく、自社のビジョン実現に向けて「どのような人材を、いつまでに、どのような方法で獲得するか」を体系的に設計し、実行することを指します。
採用戦略、採用計画、人材戦略は混同されがちですが、それぞれ異なる概念です。
採用戦略:「どのような人材をどのような手法で獲得するか」といった方向性を定める施策
採用計画:「今年度何人採用するか」といった短期的な実行計画
人材戦略:採用だけでなく育成や配置も含む包括的な人事施策全体
採用戦略は人材戦略の一部として位置づけられ、採用計画は採用戦略を具体的な行動に落とし込む役割を担います。
これらを正しく理解し、連動させることが重要です。
日本の生産年齢人口は減少すると予測され、人材不足は深刻化の一途をたどっています。
令和7年3月に公表された厚生労働省データによると、有効求人倍率は1.26倍となっており、優秀な人材の獲得競争は激化しています。
さらに、人的資本経営への注目が高まり、上場企業では人材関連情報の開示が義務化されました。
このような環境下で、経営戦略と連動した採用戦略なしには、事業の継続も成長も困難となっています。
採用の成否が企業の競争力を直接的に左右する時代に突入しました。
効果的な採用戦略を実践することで、企業は具体的にどのような成果を得られるのでしょうか。
多くの企業が採用戦略を導入した結果、定着率の向上、応募者の質・量改善、採用コストの最適化など、測定可能な成果を生み出しています。
ここでは、採用戦略がもたらす、3つの成果について解説します。
採用戦略の成果の一つは、入社後のミスマッチを防ぎ、定着率を改善することです。
ミスマッチを防ぐには、企業文化や価値観を明確に伝え、候補者との相互理解を深めることが重要です。
選考プロセスでの丁寧なコミュニケーションとリアルな職場情報の提供が、長期的な定着率向上につながります。
採用ブランディングを戦略的に実施することで、応募者数と質の両方を向上させることができます。
重要なのは、自社の魅力を一方的に伝えるのではなく、ターゲット人材が求める価値観や働き方と自社の特徴をマッチングさせることです。
競合企業との差別化ポイントを明確にし、一貫性のあるメッセージを発信することが成功の鍵です。
採用戦略により、採用コストを大幅に削減しつつ、投資対効果(ROI)を向上させることが可能です。
データに基づいた意思決定を行うことで、限られた予算で最大の成果を生み出すことができます。
重要なのは、単にコストを削減するのではなく、質の高い人材を効率的に獲得する仕組みを構築することです。
採用戦略を立案する際、何から始めればよいか迷う担当者は少なくありません。
ここでは、初めてでも迷わず実践できる「7つのステップ」を詳しく解説します。
このマニュアルに沿って進めれば、自社の状況に最適な採用戦略を体系的に構築できます。
採用戦略の第一歩は、経営戦略との整合性を確保し、現状を正しく把握することです。
まず、今後3年間の事業計画から必要な人材像と人数を導き出します。
「中期経営計画」が3年間で策定されるのと同様に、採用戦略においても3年という期間は、経営目標の変化を見越した現実的なスパンとされています。
次に、現在の採用活動における課題(応募者不足、ミスマッチ、コスト高など)を洗い出し、優先順位をつけましょう。
この段階で重要なのは、経営層や事業部門との密なコミュニケーションです。
ワークシートを活用して、必要な人材要件を体系的に整理し、採用課題を可視化しましょう。
効果的な採用活動の要となるのが、明確な採用ペルソナの設定です。
単に「優秀な人材」とするのではなく、具体的なスキル、経験、価値観、キャリア志向などを詳細に定義します。
ペルソナ設定では、必須要件と歓迎要件を明確に分け、現実的に採用可能なレベルに調整することが重要です。
また、設定したペルソナが市場に存在し、自社を選ぶ可能性があるかを検証するために、3C分析(自社・競合・候補者)を活用しましょう。
EVP(Employee Value Proposition)とは、企業が従業員に提供できる価値の総称です。
給与や福利厚生だけでなく、成長機会や企業文化、社会的意義などを含め、自社ならではの魅力を明確に言語化します。
効果的なEVP抽出には、既存社員へのインタビューが欠かせません。
なぜ入社を決めたのか、何にやりがいを感じているのかを深掘りすることで、自社のリアルな魅力を明確にできます。
競合他社との比較分析を行い、独自の強みを際立たせることで、優秀な人材を惹きつける鍵になります。
採用ペルソナとEVPが明確になったら、最適な採用チャネルと手法を選定します。
求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用など、各手法には特徴があり、ターゲットによって効果が異なります。
エンジニア採用では、エンジニア特化型のマッチングプラットフォーム「GitHub」の活用が有効です。若手採用ではSNS広告の活用が適しています。このように、ペルソナの行動特性に合わせたチャネル選択が重要となります。
コストと効果のバランスを考慮しながら複数のチャネルを組み合わせることで、より効果的な採用戦略を設計できます。
優秀な人材を獲得するには、選考プロセス全体を通じて優れた候補者体験(CX)を提供することが不可欠です。
応募から内定までの各段階で離脱率を分析し、ボトルネックを特定します。
書類選考の基準を明確化し、面接官トレーニング、フィードバックを迅速化するなど、具体的な改善施策を実施します。
特にオンライン面接では、技術的なトラブルを防ぎ、対面と同等以上のコミュニケーションを実現する工夫が必要です。
候補者の時間を尊重し、透明性の高い選考を行うことで、内定承諾率の向上につながります。
採用戦略の成果を測定し、継続的に改善するためには、適切なKPI設定が不可欠です。
応募数、書類通過率、面接通過率、内定承諾率、採用単価など、採用プロセスの各フェーズに適したKPIを設定します。
重要なのは、単に数値を追うのではなく、その数値の背景を分析し、改善アクションにつなげることが重要です。
そのためにも、週次のレビュー体制を構築し、リアルタイムで施策の効果を把握しましょう。
採用戦略の成功には、明確な役割分担と継続的な改善サイクルが必要です。
人事部門だけでなく、経営層、現場マネージャー、既存社員まで巻き込み、全社的な体制を構築しましょう。
月次の採用戦略会議では、KPIの達成状況を確認し、成果が出ている施策は横展開、課題がある部分は改善策を検討します。
このようにPDCAサイクルを迅速に回すことで、市場の変化に柔軟に対応し、常に最適な採用活動を実現できます。
採用戦略の立案において、フレームワークを活用することで思考が整理され、抜け漏れを防ぐ強力なツールとなります。
フレームワークを採用領域に応用すれば、より体系的で説得力のある戦略を構築することができます。
ここでは、実践で即座に活用できる以下3つのフレームワークを、具体的な戦略採用の方法を交えて解説します。
これらのツールを使いこなすと、複雑な採用課題もシンプルに整理できます。
3C分析を採用戦略に応用することで、自社の採用における立ち位置を客観的に把握できます。
この3つの分析を活用することで、競合との差別化を図り、独自のポジショニングを確立できます。
内外の環境を多角的に分析できるSWOT分析は、採用戦略の方向性を定める際に有効なフレームワークです。
さらに、クロスSWOT分析により、強みを活かして機会を掴む具体的な戦略を導き出せます。
例えば、強み×脅威では、強みを活かして外部のリスクに対抗する戦略を立てる際に有効です。
候補者の行動と心理を可視化するペルソナジャーニーマップは、採用プロセスの改善に威力を発揮します。
まず、認知、興味、応募、選考、内定、入社までの各段階で、候補者がどのような情報を求め、何を不安に感じるかを詳細にマッピングします。
次に、各接点での候補者の期待値と実際の体験のギャップを特定し、改善施策を立案します。
例えば、応募段階での離脱が多い場合は、応募フォームの簡素化や必要情報を事前に提供するなどの対策が有効です。
このアプローチを通じて、候補者視点での最適な採用プロセスを設計できます。
企業規模や成長フェーズによって、効果的な採用戦略は異なります。
大企業の手法をそのまま中小企業が真似しても成果は期待できません。
ここでは、企業規模別の特性を踏まえた採用戦略の成功パターンを紹介します。
自社の状況に近いパターンから学ぶことで、実践的なヒントを得られるため精度の高い戦略立案が可能になります。
中小企業やスタートアップは、限られたリソースで大手企業と競争しなければなりません。
優秀な人材確保のためには、機動力の高さ、経営者との距離の近さ、裁量の大きさなど、独自の強みを活かすことが重要です。
例えば、社員紹介制度を充実させ、紹介による採用比率を高める方法や、地方では、UIターン支援と地域貢献をアピールし、都市部の優秀な人材を獲得する方法があります。
新潟に本社を置く「株式会社シアンス」は、UIJターン採用を積極的に進め、多様な人材を迎えることで、新たな事業開発や採用定着を実現しました。(※)
このように、低予算でも工夫次第で大きな成果を生み出せます。
大企業は、意思決定の遅さや硬直的な組織文化が課題となりやすい一方、ブランド力、安定性、充実した教育制度など多くの強みがあります。
成功している大企業は、採用のデジタル化を進め、AIを活用した書類選考やチャットボットによる問い合わせ対応で効率化を図っています。
例えば、「ソフトバンク」では、エントリーシートでAI判定を導入した結果、作業時間を4分の1に短縮することに成功しました。(※)
また、グローバル人材の獲得では、海外大学との連携や現地での採用イベント開催が効果的です。
新卒・中途・専門職それぞれに特化した採用チームを設置し、きめ細かな対応を実現している企業も増えています。
※参考: AI事例② |ソフトバンク
業界によって求められる人材像や効果的な採用手法は異なります。
各業界の特性を理解し、職種ごとの訴求ポイントを明確にすることで、ターゲット人材に響くメッセージを効果的に発信できます。
採用ブランディングとは、企業が「働く場所」としての魅力を高め、求職者から選ばれる存在になるための戦略的な取り組みです。
単なる広報活動ではなく、企業の本質的な価値を見出し、それを一貫性を持って発信することで、共感する人材を惹きつけます。
近年の労働人口減少に加え、生成AIの普及やZ世代の価値観の変化など、採用環境は大きく変化しています。
このような背景の中で、優秀な人材から「選ばれる企業」になることは、企業の競争力を維持し、持続的な成長に不可欠です。
ここでは、採用ブランディングの本質から実践方法、成功事例まで、体系的に解説します。
採用ブランディングへの投資は、短期的にはコストに見えても、中長期的には大きなリターンをもたらします。
重要なのは、表面的な魅力づけではなく、企業のEVP(Employee Value Proposition) を明確にし、それを求職者に伝わる形で表現することです。
採用ブランディングの効果は、応募者数の増加、質の向上、内定承諾率の改善、さらには既存社員のエンゲージメント向上にも波及します。
また、生成AIを活用したパーソナライズ採用やデータ分析によるターゲット戦略の最適化を組み込むことで、企業の魅力をより的確に伝え、求職者との適切なマッチングを促進できます。
採用ブランディングを成功させるには、体系的なアプローチが必要です。
特に、社員をアンバサダーとして巻き込むことも重要で、社員がリアルな声を発信することで企業ブランドを自然に広げる仕組みを構築すると、採用ブランディングの効果が高まります。
採用活動において、コスト管理とデータ活用は避けて通れない重要テーマです。
多くの企業が採用予算の制約に悩む中、データに基づいた意思決定を行うことにより、少ない投資で最大の成果を生み出すことが可能になります。
ここでは、採用コストの構造を理解し、無駄を省きながら質の高い採用を実現する方法を解説します。
さらに、誰でも始められるデータドリブン採用の第一歩として、押さえるべき指標と分析手法を紹介します。
採用コストは、求人広告費や人材紹介手数料などの「見えるコスト」と、社員の工数や機会損失などの「見えないコスト」に分けられます。
コスト削減のポイントは、まず各採用チャネルのCPA(採用単価)とROI(投資対効果)を可視化することです。
効果の低いチャネルを削減し、リファラル採用やダイレクトリクルーティングなど、コスト効率の高い手法にシフトすることで、トータルコストを削減できます。
さらに、AIチャットボットを導入することで、候補者対応の負担を軽減し、面接官の工数を最適化することも可能です。
また、生成AIを活用しした候補者スクリーニングの自動化により、初期選考の効率化と精度の高い採用を実現できます。
データドリブン採用を始めるには、まず基本的な5つの指標から着手しましょう。
これらを継続的に記録し、傾向を分析することで、採用プロセスのボトルネックを特定できます。
例えば、書類通過率が低い場合は求人要件の見直し、内定承諾率が低い場合は選考プロセスや条件提示の改善が必要です。
Googleスプレッドシートや「Tableau」「Looker Studio」などのBIツールの活用や、ATSのレポート機能をうまく利用すれば、専門知識がなくても簡単にデータ分析を始められます。
また、パフォーマンスマーケティングを活用し、データ分析をもとに広告運用の最適化を行うことも、費用対効果を向上させるには有効です。
重要なのは、完璧を求めず、まず実践することです。
採用領域におけるAIとデジタル技術の活用は、もはや選択肢ではなく必須となりつつあります。
生成AIの登場により、採用プロセスの自動化と効率化は新たな段階へと進化しています。
ここでは、2025年の最新トレンドを踏まえ、AIやHRテックを活用した先進的な採用手法を紹介します。
AI技術の進化により、採用の各フェーズでスクリーニングの精度向上、パーソナライズ化、意思決定支援が可能となりました。
書類選考の自動化:過去の採用データを学習し、自社に適した候補者を自動でスクリーニング
AIチャットボットの活用:24時間365日、候補者からの問い合わせ対応を自動化し、採用担当者の負担を大幅に軽減
AIアセスメントツールの活用:当社が提供する「Chemii!!(ケミィ)」では、候補者と企業の共感度、カルチャーマッチ度の測定が可能
また、AIによる「面接アシスタント」 の導入が進んでおり、リアルタイムフィードバックや質問の最適化 により、選考の質向上を実現できます。
適切なマッチングにより、入社後のミスマッチによる早期離職率の低下が期待できます。
ただし、AIはあくまで支援ツールであり、最終的な判断は人間が行うことが重要です。
採用DXを成功させるためには、採用管理システム(ATS)の選定が鍵となります。
選定のポイントは、自社の規模、予算、必要な機能を明確にすることです。
導入効果として、以下のようなメリットが期待できます。
最新の採用DXツールには「パーソナライズ求人レコメンド」「スキルマッチAI」 などの機能が追加され、ターゲット候補者への精度の高いアプローチが可能になっています。
採用戦略を実行する過程で、多くの企業が似たような失敗を経験しています。
ここでは、実際によく見られる以下3つの典型的な失敗事例と、それを回避するための具体的な対策を解説します。
よくある失敗の一つは、設定したペルソナと選んだ採用手法がかみ合わないケースです。
例えば、20代のデジタルネイティブ世代をターゲットにしているにもかかわらず、紙媒体の求人広告に予算を集中させるような場合です。
また、シニア層の経験者を求めているのに、SNS採用のみに注力するのも効果的とはいえません。
対策としては、ペルソナの情報収集行動を詳細に分析し、彼らが日常的に接触するメディアやプラットフォームを特定することです。
そのうえで、ペルソナごとに最適なチャネルミックスを設計することが成功の鍵となります。
採用戦略を立案しても、すぐに成果が出ないことに焦り、場当たり的な施策に走ってしまうケースも多く見られます。
特に採用ブランディングのような中長期的な取り組みは、効果が見えるまでに一定の時間を要します。3ヶ月で効果が見えないからと中断してしまっては本質的な改善には至りません。
対策としては、短期・中期・長期それぞれにKPIを設定し、段階的な成果を可視化することです。
例えば、短期では認知度向上、中期では応募者数増加、長期では定着率改善といったように、時間軸に応じた評価指標を設定し、継続的に進捗を確認することが重要です。
人事部門だけで採用活動を完結させようとして、現場の協力を得られないケースも失敗の典型例です。
現場社員が採用に無関心のままだと、面接での魅力訴求が弱くなり、入社後のフォローも手薄になりがちです。
対策としては、採用を全社的なミッションとして位置づけ、現場社員向けの説明会を実施するなど、巻き込みの仕組みを作ることです。
なぜその人材が必要なのか、採用成功が部門にもたらすメリットは何かを明確に伝えることで、現場の理解と協力を得やすくなります。
また、リファラル採用制度を導入し、社員全員を採用活動に関わる仕組みづくりも効果的です。
採用戦略の実践において、多くの担当者が直面する疑問や悩みがあります。
ここでは、特に重要な質問を3つ厳選し、実践的な回答を提供します。
限られた予算で最大の効果を出すには、費用対効果の高い施策から優先的に取り組むことが重要です。
具体的には、社員紹介制度の導入(紹介インセンティブは採用決定後の支給)、自社採用サイトの改善(無料ツールの活用も可能)、SNSでの情報発信(低コストで認知拡大)などです。
次のステップとして、採用チャネルごとの効果をデータで可視化し、最も効果の高い採用チャネルに予算を集中させましょう。
求人広告を複数媒体に分散するより、効果の高い1-2媒体に絞って活用する方が結果的に採用単価を抑えられます。
経営層の理解を得るには、採用の重要性を「経営数値」で語ることが不可欠です。
例えば、欠員1名あたりの機会損失額、採用遅延による売上への影響、離職による損失コストなどを具体的な金額で示します。
さらに、採用戦略の導入による期待効果を、定着率向上による採用コスト削減額、生産性向上による売上貢献額などの数値で表現することも重要です。
加えて、他社の成功事例も交えながら、投資対効果を明確に提示することで、採用は「コスト」ではなく「未来への投資」であることを理解してもらえるでしょう。
定期的な進捗報告や成果の可視化も、経営層の信頼を得るうえで効果的です。
まず業務の優先順位を明確にし、コア業務(戦略立案、面接、クロージング)に集中できる環境・体制を整えましょう。
定型業務は極力自動化・外注化し、採用管理システムの導入、応募受付の自動返信設定、一次面接のオンライン化などで効率化を図ります。
また、現場社員を巻き込む体制づくりも重要です。
例えば、面接官トレーニングを実施し、一次面接を現場に任せることで担当者の負荷を分散できます。
一人で採用業務を担当する場合、すべてを完璧にこなそうとすると苦しくなります。
月1回でも採用全体を俯瞰する時間を確保し、PDCAを回すことが成功への近道です。
また、採用代行(RPO)やコンサルティングサービスを活用し、外部のリソースやナレッジを借りるのも一つの手段です。
一人でやりきれない業務や、ノンコア業務を外部委託に出すことで、採用活動の最適化を図りましょう。
ここまで採用戦略について包括的に解説してきました。
情報量が多く、何から手をつければよいか迷う方もいるでしょう。
しかし、たとえ小さな一歩でも、継続することで必ず大きな変化につながります。
採用戦略の成功には、完璧な計画よりも、まず行動を起こすことが何より大切です。
とはいえ、担当者のリソースが不足している場合や、戦略がうまく機能していない場合は、専門的な知見のある外部業者に依頼しましょう。
当社では、採用における実績と経験をもとに、企業に最適な提案をしています。
戦略的な採用の効率化を図りたいとお考えの方は、お問い合わせからご相談ください。
レジェンダ担当者のコメント
採用戦略は「描く」ことが目的ではなく、「動かす」ことが本質です。どれだけ精緻に設計されていても、現場で実行されなければ成果にはつながりません。多くの関係者が関わる大手企業では、全体最適が難しく、現場の理解を得るまでに時間がかかったり、社内調整の負荷が高かったりすることで、柔軟な見直しがしづらい傾向があります。一方、中堅企業では、戦略が経営と直結せず、現場で形骸化してしまうケースも少なくありません。
共通する鍵は、戦略と現場の“接続”をどう設計・運用するか。私たちのRPOは、戦略の意図を踏まえた評価設計や業務フローの再構築、AI支援の導入などを通じて、現場に落とし込むための運用体制づくりをご支援しています。
採用戦略の実行にお悩みの方は、ぜひお役立てください。
この記事の監修者
金濵 祐香子
採用支援事業部
■経歴
通信・IT・メーカー・製造・小売など、さまざまな業界のクライアントを担当し、新卒・中途採用の支援をPMとして推進。常駐・遠隔の両形態で支援を行い、リクルーター・面接官・バックオフィス統括等の役割を担いながら、選考設計から運用まで一貫して支援している。

採用ブランディング完全ガイド
全10ページの
実践ステップ搭載
無料ダウンロード
資料を受け取る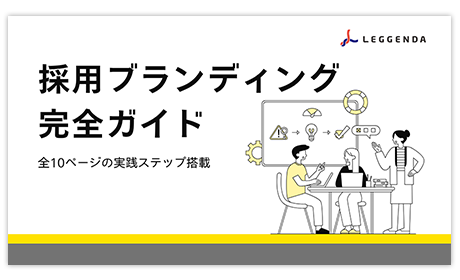 資料を受け取る
資料を受け取る
関連記事
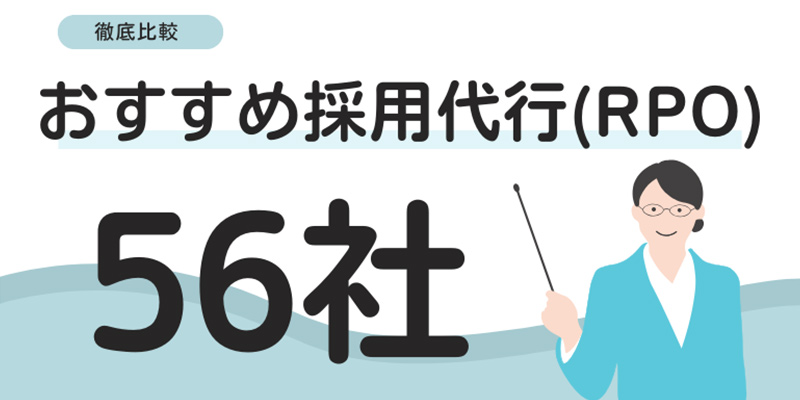
採用コラム2024.09.06【2025年最新版】採用代行(RPO)おすすめ56選!料金・サービス内容を徹底比較

採用コラム2024.08.30採用代行(RPO)の費用相場は?おすすめの代行会社3つと4つのメリットも紹介

採用コラム2024.06.07採用代行(RPO)のメリットとデメリット!選定のポイントや事例も解説

採用コラム2024.08.16採用代行(RPO)が向いている企業の特徴6選 | メリット/デメリットと導入の3つの注意点も紹介

採用コラム2024.06.28採用代行(RPO)と人材紹介の違いとは?メリットや行政への許可など8つの観点から解説

採用コラム2024.06.21採用代行の市場規模は?RPOの将来性やアウトソーシングによるメリット・デメリットを解説
人気記事